コーヒー豆の焙煎とは?生豆との違い

皆さんは、コーヒー豆が黒い理由を知っていますか?
「黒い理由?」
そう。コーヒー豆はもとから黒いわけではないんです。正確にいえば豆ですらありません。
コーヒー豆は、もとはコーヒーノキから収穫されるコーヒーチェリーと呼ばれる赤い実です。
ここから種を取り出し、洗って乾燥させたものがコーヒー生豆と呼ばれます。
生豆は、そのままだと味や香りがほとんどありません。ですが、煎って加熱することで生豆の成分が化学変化を起こし、美味しいコーヒーが淹れられる豆になります。これを焙煎と呼び、市場に出回っているコーヒー飲料は焙煎された豆から淹れたものになります。
焙煎が適切であれば、風味豊かな良い苦みが生まれます。ですが、煎りすぎたり、煎りが浅すぎたりすると、良い風味を打ち消す嫌な味が生まれてしまいます。
コーヒーの味を決める要因は他にもありますが、今回は焙煎に絞って見ていきましょう。
コーヒー豆の焙煎によって味はどう変わる?
浅めの焙煎は苦みとコクが少ない代わりに軽やかでフルーティ、深めの焙煎は苦みがあり香ばしくなります。
焙煎の度合いは大きく分けて、「浅煎り」「中煎り」「深煎り」の3段階。
ここからさらに細分化して8段階に分けることが一般的です。
浅煎り

ライトロースト
うっすらと焦げ目がついた小麦色。
主にカッピングテストに使用されています。焙煎の種類や豆の品種によっては青臭さが残ってしまう場合があります。
※カッピングテスト:コーヒーを口に含み、香りや味などの品質を確かめること。
シナモンロースト
少し焦げが強くなり、シナモンのような色になります。
豆由来の様々なフルーツのような風味を感じることができ、浅煎り派にはたまらない煎り具合と言われています。
中煎り

ミディアムロースト
このあたりから、一般的に想像されるコーヒーの苦みや香りがわずかに出てきます。酸味は少しまろやかに。
スッキリとした味わいで、アメリカンコーヒーに使われることが多いです。そのため、アメリカンローストとも呼ばれています。
ハイロースト
酸味が残りつつも、苦みや甘みが強く出てくるようになります。
よく日本で提供される中煎りレギュラーコーヒーは、だいたいハイローストになります。
深煎り

シティロースト
最も一般的な焙煎度合いと言われています。酸味が消え始め、だんだん皆さんが想像する「苦いコーヒー」の味に近づいてきます。
ハイローストと並んで、よく飲まれる焙煎度合いのようです。エスプレッソに使用することもあります。
フルシティロースト
徐々に酸味が薄くなり、代わりに苦味が前面に出てきます。香りも一層強くなってきました。
このあたりの焙煎度合いから、アイスコーヒー、エスプレッソに使われることが多くなってきます。
ちなみに「シティロースト」「フルシティロースト」の「シティ」は、「ニューヨークシティ」のことです。
フレンチロースト
コーヒー豆の油分が表面を覆い始めます。
酸味は消え、苦みが強くなるため、ブラックよりもミルクやクリームと一緒に飲む方法に向きます。もちろんブラックで苦みを楽しんでも良し。
イタリアンロースト
色は真っ黒。ここまでくると、油分で表面がつやつやになっています。
非常に苦みが強く、エスプレッソやカプチーノなど、名前のとおりイタリア系のコーヒーに向く焙煎です。
しかし、お店によって煎り具合の判断は異なる場合があります。
あるお店の中煎りが他のお店では深煎りだったりすることもあるので、あくまで目安として考えてください。
コーヒー豆の焙煎度合いによる地域差(世界と日本)
地域によって好まれる焙煎度合いは異なります。今回は3つの地域に分けて紹介します。
ヨーロッパ
一言でヨーロッパと言っても、北と南では好まれるものが違います。
コーヒーの消費量が世界一の地域である北欧では、酸味やフルーティな味わいが好まれるため、浅煎りが主流です。お茶のような感覚でさらっと飲む方が多い様子。
一方フランス、イタリアと南に下っていくと、(フレンチローストやイタリアンローストという名前から察せられる通り)深煎りが主流になってきます。エスプレッソやカプチーノにミルクやクリーム、砂糖を加えて飲むのが主流です。もちろんブラックで飲むこともあります。
スペインではなんとアルコールをいれることも。
アメリカ
ボストン茶会事件がきっかけで、紅茶に変わる新たな飲料として注目されたのがコーヒーでした。
これまでおきた3回のコーヒーブーム(後述)の中で、好まれる焙煎は変わってきています。
現在の主流は浅煎りです。
とはいえ、豆によって焙煎具合を変えるのが流行りの昨今。特に豆の味がわかる浅煎りがよく飲まれるというだけで、中〜深煎りも変わらず愛されているようです。特にシアトルでは、深煎りの文化が根付いている様子。
セカンドウェーブ(後述)の反動か、自家焙煎して提供するお店が多いそうです。
日本・中東
コーヒー後進国の日本とアジア。割とアメリカの流行を追いかけているようなところがあります。
現在流行しているのは浅煎りですが、日本では昔から深煎りの味わいも楽しまれています。
一方、中東は深煎りが主流です。トルココーヒーを筆頭に、淹れ方が面白いものが多いため、調べてみると楽しいかもしれません。
コーヒー豆の焙煎度合いと時代
さて、焙煎度合いと地域差について触れたなかで、セカンドウェーブと言った言葉がでてきました。
コーヒー業界では一般的にコーヒー豆の焙煎度合の嗜好の変化やブームを”ウェーブ”に分けて説明します。
今のところ、コーヒーブームは過去3回起きたと言われています。
その中で、どういった焙煎が主流だったのかを見ていきましょう。
ファーストウェーブ〜手軽にコーヒーを〜
1800年代〜1960年代初頭。
真空包装の技術が開発され、コーヒーが世界中で大量に消費されるようになりました。
特にインスタントコーヒーの功績は大きく、手軽に楽しめる飲料として人々の間に広がっていきました。
このときの主流は浅煎りです。
まだまだ質より量の時代なので、品質にばらつきがあります。
日本では1960年代〜1990年代にファーストウェーブがやってきました。
セカンドウェーブ〜シアトルからやってきた〜
1960年代初頭〜1990年代。
この頃から、味・品質を重要視する流れが起き始めます。
1971年に開業したスターバックスを筆頭に、「シアトル系」のコーヒーが一斉を風靡しました。テイクアウト可能な紙コップ、自分好みにカスタマイズするエスプレッソが流行しています。主流は深煎り。
日本では、やや遅れて1996年頃にセカンドウェーブが訪れています。
サードウェーブ〜味を極めろ〜
2000年代初頭〜現在、真っ只中のサードウェーブ。
これまでは、様々な種留意の豆をブレンドして淹れるのが主流でしたが、ここにきてシングルオリジンという、「高品質な一種類の豆で、一杯ずつコーヒーを淹れる」という考え方が生まれます。
浅煎りでコーヒー豆自体の味を楽しむのが主流です。とはいえ、深煎りブレンドコーヒーもまだまだ健在。好みにあったものを探しましょう。
コーヒー豆の焙煎に正解はない!お店ごとの違いを見つけよう!

同じ豆を使っていても、焙煎具合によって味は大きく変わります。現在は浅煎りが流行していますが、口に合わなければ、もっと焙煎したものを試してみてもいいでしょう。
また、お店によっても珈琲の味は変わります。例えば、同じモカでも、お店毎に産地や焙煎度合いが違うため、味に違いが出てきます。飲み比べてみるのも楽しいですよ。
IMOM COFFEE Nagya Staでは同じ豆を焙煎度合いごとに変えており、同じ産地で焙煎度合いだけが違う豆を飲み比べることができます。ぜひ来店して、好みの味を探す楽しみを味わってみてください。
また、焙煎自体に興味のある方は、初心者向けの焙煎セミナーも開催しておりますので、ぜひこちらもご覧ください!


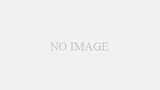


コメント